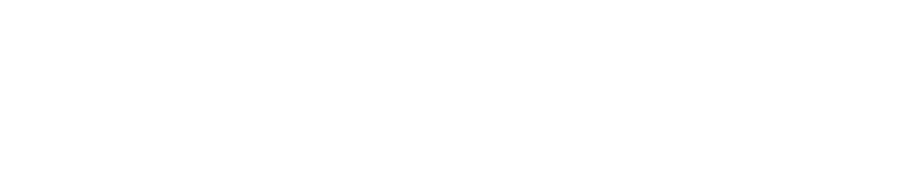欧州初!雑草の生物的防除資材として植食性昆虫を導入
イタドリは、19世紀にシーボルトにより日本(長崎)からヨーロッパへ持ち込まれました。イギリスでも当初は観賞用として歓迎されましたが、繁殖力旺盛で野生化し、アスファルトやコンクリートを突き破るなど猛威をふるっています。

コンクリートの割れ目から新芽を伸ばす
イタドリ(九州大学構内にて)
イギリスではイタドリの生物的防除資材として日本から植食性昆虫や植物病原性微生物を導入することが検討され、国際生物的防除研究所(CABI,イギリス)と協力して研究を進めてきました(共同研究に関する記事が2009年8月16日の朝日新聞朝刊に掲載されました)。
その結果、イタドリマダラキジラミはイタドリのみを餌とする(他の植物に害を与えない)ため環境に悪影響を及ぼさないこと、イギリスでも越冬可能であることなどが確認され、イタドリマダラキジラミを日本から導入することが決定されました。
イタドリマダラキジラミによる生物的防除
ここからは、実際に行った調査をもとに、イタドリとイタドリマダラキジラミについてもう少し詳しく説明したいと思います。
イタドリ Fallopia japonica について
イタドリはタデ科の多年生草本で、冬季に地上部が枯れ、地下茎で越冬します。高さは、日本ではせいぜい2mくらいですが、イギリスでは3mを超えます(Beerling et al., 1994)。
繁殖力が強く、生物多様性の損失や建造物の破壊が起きるなど、イギリスでイタドリによる被害が拡大しました。化学的防除を行うには3,000億円以上必要との試算があります(Defra, 2003)。
国際自然保護連合(IUCN)が定める「世界の特定外来生物ワースト100(イタドリのページ)」に指定されました。

川沿いに繁茂するイタドリ
(英・グラスゴー、ケルビン川にて)

イタドリに破壊された壁
(英・レディングにて)
イギリスの国家河川局による1994年と1996年の調査から、イタドリの最も有効な防除法は生物的防除(天敵の導入)であると示唆されました。
イギリスのイタドリおよびイタドリ被害写真は、黒瀬大介氏(九州大学農学部植物病理学研究室 卒)よりご提供いただきました。
イタドリマダラキジラミ Aphalara itadori について
カメムシ目タデキジラミ科の昆虫です。北海道から奄美大島まで広く分布します。体長は約2mmで、その姿はセミに似ています。

室内実験中のイタドリマダラキジラミ
幼虫から成虫までずっとイタドリを吸汁するスペシャリストで、室内飼育ではイタドリを枯死させることが可能です。
国際生物的防除研究所(CABI)が日本でイタドリの天敵昆虫186種を調査した結果、イタドリマダラキジラミがイタドリの生物的防除資材として最も適していました(CABI, 2007)。
また、イタドリに近縁な植物を中心に19科90種で寄主範囲の調査を行ったところ、イタドリ以外ではほとんど産卵せず、生育も不可能でした(Shaw, 2009)。
つまり、イタドリマダラキジラミはイタドリのみを加害し、他の植物に害を与えないため、生物的防除資材として極めて優れていると言えます。
生物的防除資材として実用化するために
イタドリマダラキジラミの野外での生態はほとんど解明されていませんでした。しかし、イタドリ駆除に利用するためには、イタドリマダラキジラミの生態、特にイタドリの枯れる冬にどのように越冬しているのかを知っておく必要があります。
イタドリマダラキジラミの野外での発生消長
個体数調査
2008~2009年、福岡県宮若市犬鳴峠に自生するイタドリについて、葉上のイタドリマダラキジラミの個体数を調査しました。
その結果、1年の間に発生のピークは4回であることを確認しました。また、春と秋に採取された個体は夏の個体と比べて体色が暗化していることがわかりました。
翅の長さ
2008年に得られた個体について翅の長さを比較すると、メスの方がオスよりも長いことがわかりました。また、春と秋に採取された個体は夏の個体より翅が長かったことから、秋の個体と翌春の個体は同一の世代であると推測されます。
以上の結果より、イタドリマダラキジラミの世代交代は年3回であり、第3世代が越冬していると考えられます。
短日条件による越冬態への変化
室内で日長条件を変えて飼育したところ、次のような違いが見られました。

長日条件(14L:10D, 25℃)
・体色は茶色
・翅が短い
・産卵する
→ 第1、第2世代がこの特徴に当てはまります。

短日条件(10L:14D, 20℃)
・体色は暗化傾向
・翅が長い
・産卵しない
→ 第3世代(越冬世代)がこの特徴に当てはまります。
野外での越冬実験(1月上旬~4月上旬)

イタドリマダラキジラミが越冬するための必要条件を確認するため、九州大学農学部附属演習林のスギとアカマツの緑枝に袋をかぶせ、その中に短日または長日条件で室内飼育したイタドリマダラキジラミ10匹(オス5匹、メス5匹)を放す、という実験を行いました。
その結果、短日条件で飼育した個体のみ越冬できていることが確認されました。また、スギ、アカマツともにイタドリマダラキジラミによる被害は見られませんでした。
越冬後の産卵実験

短日条件で飼育して越冬した個体を、さらに室内で3週間飼育(12L:12D, 25℃)したところ、産卵を確認しました。
つまり、イタドリマダラキジラミは越冬前には産卵せず、越冬後の春に産卵を行っていると考えられます。
生物的防除資材として実用化するために<まとめ>
- イタドリ以外の植物では成育できない
- 常緑樹上で成虫の状態で越冬するが、樹木は加害しない
- 越冬態が産卵するためには冬を経験する必要がある
イタドリマダラキジラミのこれらの特性は、イギリスのイタドリの生物的防除資材として高く評価されました。