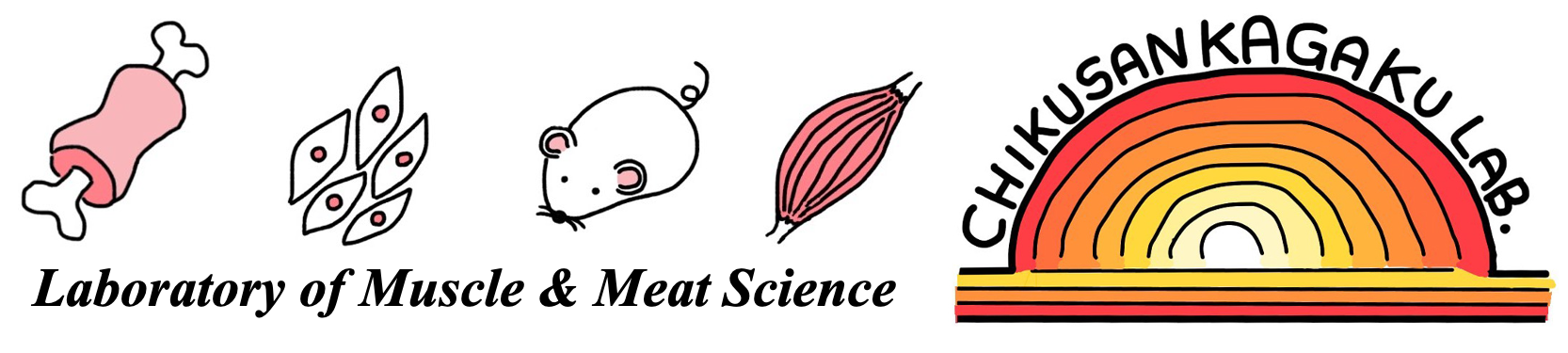研究室の沿革をご説明します。
研究室設置までの黎明期
昭和21(1946)年4月、九州大学農学部畜産学科は農学科から分離独立し、新しい学科として発足した。新設当時における畜産学科は、畜産学第1講座、畜産学第2講座及び動物学第1講座の3講座で構成されていた。昭和29(1954)年4月に、畜産化学の前身である畜産製造学講座が設置された。この講座の研究分野は、講座名の示す通り畜産製造学に関するもので、各種畜産食品の性状とその利用、加工、保存などに関連した部門であった。講座の創設当時は、畜産学第1講座担当の教授丹下正治と畜産学第2講座担当の教授加藤嘉太郎が同講座を分担し、講座の充実と発展のために種々尽力を続けた。
1. 安藤則秀教授(昭和31[1956]年~昭和47[1972]年)
昭和31(1956)年4月宮崎大学農学部教授安藤則秀が九州大学に転任し、はじめて専任の畜産製造学講座担当教授が決定した。まもなく助手として東大農学部から加香芳孝(後に鹿児島大学教授)と九大農学部農産製造学から永田致治の2名が着任した。昭和37(1962)年3月からは畜産学第2講座に所属していた講師赤司景が畜産製造学講座へ転属となった。昭和40(1965)年10月には加香芳孝助手が鹿児島大学助教授として転出し、その後任として伊藤肇躬(畜・昭38)が助手に任命された。日本においては乳製品工業はその発展の歴史が古く、従って、この方面の研究に従事する者の数も多く、研究活動も盛んであった。これに対して肉製品工業は、研究者の数も少なく研究の進展も遅れていた。
講座としては、肉製品工業の発展に協力するための基礎的研究にその主力が注がれた。肉製品の発色、変色の問題、保水性の問題、保存の問題などである。本講座では主としてこれらの問題を中心にして研究が進められて本講座では主としてこれらの間蓮を中心にして研究が進められ、肉製品に関する研究では、肉製品の発色、変色に及ばす発色剤、還元剤、ニコチン酸アミド、各種リン酸塩などの作用機構、肉製品中の亜硝酸塩定量法、亜硝酸塩の挙動に及ぼす各種食品添加物の影響、肉製品の発色に及ぼす筋組織各画分の影響、食肉脂肪の酸敗とその防止法などが詳しく追究された。安藤教授は食肉研究者国際会議の日本代表役員を務めるかたわら、ヨーロッパ各地、オーストラリア、ニュージーランドなどの大学や研究所を数多く訪問し、畜産製造学の分野における国際的交流連携の面において多大の成果をあげた。昭和47年3月、安藤教授は定年により退職し、名誉教授の称号を授与された。単名の著書に「牛乳と乳製品の理科学」、「肉と肉製品の理科学」、「卵と卵製品の理科学」(地球出版)がある。
2. 深沢利行教授(昭和47[1972]年~平成4[1992]年)
安藤則秀教授が退官した後、2代目の教授として、北海道大学農学部助教授深沢利行が昭和47(1972)年10月着任した。着任時の年令は44歳であり、当時の農学部教授就任時の平均年令に比較するときわめて若い教授就任であった。深沢教授着任後、間もなく赤司景講師が助教授に昇任、昭和50(1975)年琉球大学教授に昇任・転任したのをうけて、永田助手が助教授に昇任、その助手の席を大学院生六車三治男(畜・昭49博)が継いだ。昭和56(1981)年永田助教授が麻布大学獣医学部助教授に転任した(その1年後に教授昇任)のち、昭和57(1982)年伊藤助手が助教授に昇任した。以後、深沢教授の退官までこの陣容で推移した。深沢教授の着任時の我が国養豚業界では丁度豚肉の異常肉(業界ではフケ肉とかムレ肉と呼ばれた肉で、専門用語ではPSE豚肉と称する劣悪な肉質の豚肉)の発生が大きな経済問題となりつつあった頃であったことから、研究室全体の研究テーマとしてPSE豚肉について活発な研究が進められた。深沢教授は、電子顕微鏡及び光学顕微鏡に優れた技術を有していたことから、「筋肉乃至食肉の形態と機能乃至食肉特性との関連性」、とりわけ、「Z線の構造と食肉特性との相関」に大きな関心を払い、その分野の研究に最も情熱を注いだ。また、食肉加工業界において、異種蛋白質(大豆蛋白質製品、乳蛋白質製品)が主として増量剤として使用される動きに対応して、「それら異種蛋白質の使用が食肉加工品の物性に及ぼす影響を調査する研究」にも少なからぬ関心を払われた。赤司景助教授は、「畜産食品に及ぼすリゾチームの防腐効果等に関する研究」で数件の特許を取得する等、きわめて実用性に富む研究を行い、業界に多大の貞献をした。リゾチームは畜産食品に利用された恐らく最初の天然物由来の抗菌剤である。赤司助教授のこのアイデアは今日でも多くの食品に生かされている。安藤教授時代から続けられていた「食肉中の発色促進因子に関する研究」も、主として永田助教授によって進められた。 深沢教授時代の研究を振り返る時、その前半は、折しも筋肉生物学の隆盛の時代で、筋肉生物学における発見を食肉科学に応用する、いわゆる、食肉生化学の研究が容易に進められ得る環境にあったことは、また、この分野の研究に従事する研究者がこの時期一時的にきわめて多く存在し、互いに競い合う如く研究を進められたこととも相侯って、きわめて幸運な時代であった。初代の安藤教授が東大農芸化学の研究の流れを体現した「学究的な研究指導方針」であったこととは対照的に、上述の如く、深沢教授は北大農学部の伝統と理念とも言うべき「実学的研究」を実践した、と言える。深沢教授は、日本畜産学会評議員及び編集委員、日本食肉研究会評議員及び同監事、西日本畜産学会評議員、日本農芸化学会西日本支部評議員等を歴任した。民間では、財団法人伊藤記念財団専門委員会委員長を永年つとめた。
3. 伊藤肇躬教授(平成4[1992]年~平成16[2004]年)
深沢教授退官の後をうけて、助教授伊藤肇躬が平成4(1992)年6月に3代目の教授に就任した。翌平成5(1993)年3月助手六車三治男が助教授に昇任、平成5(1993)年5月に江本由美子(九大理・生物)が大分医科大学助手から転入、平成9(1997)年12月まで在籍した後、古巣の理学部生体高分子学講座助手へ転出した。代わって、平成10(1998)年4月から林利哉が助手を勤めた。平成10(1998)年7月、六車助教授は宮崎大学教授に昇任、平成12(2000)年4月、池内義秀が新潟大学助教授から転任した。平成13(2001)年4月、林助手の名城大学講師への転出をうけ、同平成13(2001)年10月から辰巳隆一が北海道大学農学部助手から転任した。
平成12(2000)年大学院重点化の達成と学府・研究院制度の導入に基づき、大幅な組織改編が行われ、畜産製造学講座は旧生物化学講座、旧栄養化学講座、旧食糧化学講座と合同して生物機能化学という大講座になり、旧農芸化学科、旧食糧化学工学科および旧水産学科の一部と合併して、生物機能科学部門を構えることになった。この時、研究室名を「畜産製造学」から新たに「畜産化学」へと変更した。
教授昇任後、伊藤教授は、安藤教授時代の研究を「食肉加工業発展期の基礎研究の時代」、深沢教授の時代を「食肉加工における原料肉の利用学の時代」と捉え、来たるべき第三世代の研究の主題は「食肉の栄養と生理活性物質解明の時代」と考え、それまでの自身の主たる研究テーマであった「筋肉の死後硬直とその人為的調節による肉質調節に関する生理・生化学的研究」をはじめとする筋肉乃至食肉蛋白質に関する生理・生化学的研究を整理し、「食肉の栄養の再評価と機能性に関する研究」、「新規筋肉細胞成長因子の純化と同定」の研究に着手し、その明らかにされた成果は、“日本人レベルの牛脂の摂取は健康に必ずしも有害ならず”、“筋肉中には内在性の運動神経依存型筋肉細胞増殖因子S-マイオトロフィンが存在し、筋肉の成長を促進する仕組みに関与している”、“牛肉摂取は成長期の哺乳動物の性ホルモン分泌を加速する”、“運動と良質蛋白質栄養の組み合わせは血中インスリン様成長因子1(IGF-1)濃度上昇と成長促進をもたらす”等で、これらの研究は食肉摂取と健康との関係に関する従来の偏った理解を改めることに貞献したであろう。このような食肉の機能性あるいは筋肉の新規生理機能物質の研究を一歩進めて『筋肉は単なる収縮機械に留まらず、第三の生理機能を有する器官である』との作業仮説を掲げて新たな研究に着手したのである。これらの研究に加えて、耐塩性酵母による発酵を利用した新しい食肉加工法の開発、新しいタイブのフローズンヨーグルトの開発に関する研究なども行った。
伊藤教授は永年に亘り2代目教授の深沢教授を補佐したこともあって、深沢教授の理念たる「実学的研究」を部分的には継承しつつも、初代の安藤教授の最晩年の門弟であったことから、むしろ安藤教授の目指された「学究的な研究理念」への回帰の側面の方が大きいように見受けられる。六車助教授は、深沢教授の最晩年時代にZ線の構造と機能の研究から発展した細胞骨格蛋白質の一つであるタリンのアクチンあるいはビンキュリンとの結合に関する研究に成果を挙げたはか、乳蛋白質製品と肉蛋白質の混合系のレオロジー、蛋白質接着酵素トランスグルタミナーゼの肉製品への利用等に関する研究を進めた。池内助教授の主な研究課題は「筋肉蛋白質への超高圧処理の影響と利用」、「アクチンの熱変性のメカニズム」等の従来からの研究課題に加え、伊藤教授と協同して「筋肉乃至食肉の生物機能化学」に関する研究も進めている。江本助手は豚脊髄からの細胞凝集阻害因子の純化と構造解析及び機能解析に関する研究に取組み、苦難の末ようやくに純化に成功した。この種の阻害因子は、医学面において、ガン組織の肥大阻害乃至はガン細胞の転移阻害因子としての作用が期待されるものである。江本助手の後任の林助手は、新規筋肉細胞成長因子S-マイオトロフィンの純化と同定の研究を担当した。
このように深沢教授時代から伊藤教授時代にかけて研究内容が大きく変化しつつあることの背景には、九大農学部でも進行しつつあった大学の組織改変の流れと食品化学分野における研究の必然的転換と展開の強いモーメントがある。即ち、畜産製造学は従来の食品加工学的あるいは畜産物利用学的研究から「食と健康」さらには「家畜由来生理活性物質の化学」を目指した生物機能化学を意識した「畜産化学」へとシフトレバーを切り替えたのである。
4. 池内義秀教授(平成16[2004]年~平成28[2016]年)
伊藤教授が退官後、助教授池内義秀が平成16[2004]年4月に4代目の教授に就任した。同平成16(2004)年10月助手辰巳隆一が助教授(平成19[2007]年より准教授)に昇任、代わって、平成17(2005)年4月から水野谷航が京都大学農学研究科から助手(平成19[2007]年より助教)に着任した。平成28(2016)年に池内教授が退官、令和元年(2019)年4月に水野谷助教が麻布大学 獣医学部 動物応用化学科 准教授として転出した。
池内教授は、主要な研究課題であった「筋肉蛋白質への超高圧処理の影響と利用」も継続しつつ、伊藤教授までの「食肉の栄養と生理活性物質解明の時代」のテーマを発展させるため、京都大学農学研究科栄養化学研究室で博士課程を修了した水野谷航助教と共に取り組んだ。また、S-マイオトロフィンを含めた筋肉細胞増殖因子を網羅的に解析した。辰巳准教授は、骨格筋の肥大、再生機構に重要な役割を果たしている筋幹細胞(衛星細胞)の活性化及び休止化機構に着目し、研究を進めた。水野谷助教は、成熟動物における骨格筋の筋線維型を栄養生理学的に制御するための研究を進めた。
従って、第4世代の畜産化学の方向性は、安藤教授から継承される「学究的な研究理念」に根付いた骨格筋組織そのものの特性の解明を一つの柱とし、さらに動物性タンパク質産生効率の向上、そして単なるタンパク質源ではない食肉の新たな栄養機能性発見を目指した「実学的研究」にも力を入れていくことであった。また、最大の目標は、古来より人類に食され、愛されてきた食肉の価値を科学的に証明し、同時に食肉の産生効率を上げることで、より多くの人々に食肉を理解し食してもらうことであった。
5. 辰巳隆一教授(令和元年[2019]年~現在)
池内教授の退官から3年半後、准教授 辰巳隆一が令和元年(2019年)10月より5代目の教授に就任した。令和2(2020)年10月から北海道大学 大学院農学研究院 畜産科学分野 助教 鈴木貴弘が准教授として着任した。
辰巳教授は、主要な研究課題である「筋幹細胞(衛星細胞)の活性化機構」に関して、キーファクターである肝細胞増殖因子の化学修飾にフォーカスを当てたプロジェクトとともに、「衛星細胞が分泌する多機能性の細胞制御因子を介した筋線維型の新奇制御機構の解明」について鈴木准教授とともに取り組んでいる。さらに、衛星細胞が局在する環境に応じて機能や動態に変化が起こる現象について、その要因を追求するプロジェクトを立ち上げている。
第5世代の畜産化学では、組織細胞生物学、分子生物学、および生化学的視点から筋肉・食肉科学の学術的理解を深めるための基礎的研究活動が展開されている。